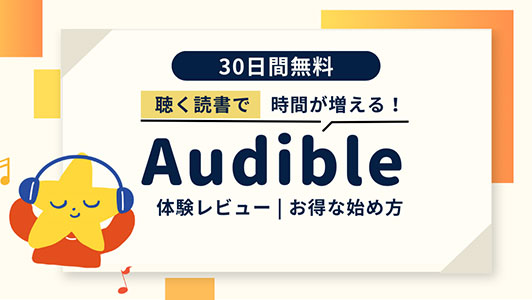読むだけで勉強の意欲が湧く1冊『「わかる」とはどういうことか』
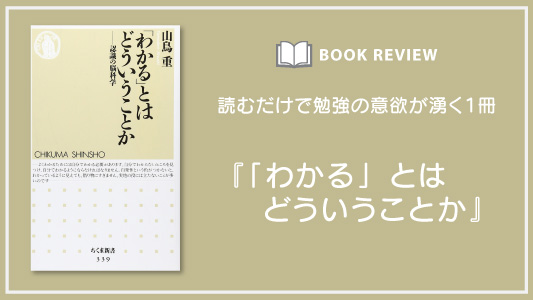
〔前略〕犬、猫、牛、馬、鳥、鳩だけしか動物を知らない、と考えてみてください。その場合はこの六種の動物がその人の知識の網の目になります。この人がもしキツネを見かけたとしたら、犬みたいな動物と判断するでしょう。あるいは、犬そのものと判断するでしょう。〔中略〕網の目が細かくなると判断も細かくなります。すべて「犬」では満足できず、犬は犬でもスピッツか、チンか、コッカースパニエルか、ということになるでしょう。〔中略〕知識の網の目ができると、何がわかっていて、何がわかっていないのかがはっきりするようになります。網の目が変なものをひっかけてくれるのです。〔後略〕
引用:「わかる」とはどういうことか 第6章「わかる」ためにはなにが必要か
こんにちは、むのです。
この記事では、読むだけで「わかる」という感覚の仕組みを理解し、学習意欲が湧いてくるおすすめの1冊を紹介します。
- 「わかる」とはどういうことなのか?
- 勉強が「わかった」とはどういう状態なのか?
- なぜ勉強することが大事なのか?
- 勉強はできるようになりたいけど、何から始めればいいかわからない
このような疑問を持つ人に読んで欲しい、大きなヒントを得られる1冊です。
キーワードは「知識の網を編む」。
学校や家庭では教えてもらえない、勉強の本質が詰まっています。
きっと目からウロコを体験できるはず!
『「わかる」とはどういうことか』概要
著者紹介
山鳥重(やまとり しげる)
日本の脳科学者で、特に認知や記憶に関する研究で知られる。
医学博士であり、脳科学の視点から教育や学習に関する研究も行っている。
本書では、脳が情報をどのように整理し理解するのかを、専門的な視点でわかりやすく解説。
本の簡単な内容
この本は、私たちが「わかる・わかった・腑に落ちた」と感じる仕組みを脳科学の視点から解説する本です。
「わかる」とは単に情報を知ることではなく、それを整理し、関連付け、自分の知識のネットワークに組み込むことです。
本書では、このネットワークのことを「知識の網の目」という例えを用いて、感覚的にも理解しやすい説明をしています。
さらに、「わかる」にはさまざまな種類があり、それを脳がどのように処理するのかが具体例とともに説明されています。
本の目次紹介
- 第1章 「わかる」ための素材
- 第2章 「わかる」ための手がかり―記号
- 第3章 「わかる」ための土台―記憶
- 第4章 「わかる」にもいろいろある
- 第5章 どんな時に「わかった」と思うのか
- 第6章 「わかる」ためにはなにが必要か
- 終章 より大きく深く「わかる」ために
この本をおすすめする理由
「わかる」という状態を知ることで勉強の効率が上がるから
この本を読むことで、私達が普段漠然と感じている「わかる」という感覚が、脳のどのような動きによって起こっているのか、その仕組みを知ることができます。
その、「わかる」動きを起こせるような勉強方法を取ることで、効率的に物事を理解していくことができます。
勉強の本質が理解できたから
私はこれまで、「勉強」とは情報を詰め込む苦しい行為で、「わかる」とは「正しい答えを覚えること」だと思っていました。
しかし本書で、勉強の意義は「知識の網を作る」ことであるという例えに触れ、学ぶ意味がすとんと腑に落ちたのです。
知識の網目

著者は、この「知識の網の目」を増やすことでさらに新しい知識を獲得し、理解することが可能になると説いています。
網の縦糸・横糸一本一本がなにかの知識です。それらが組み合わさることにより、別の情報に反応したり、応用ができるということです。
網の目が荒い人は、その隙間からどんどん知識や情報が溢れてしまいます。
つまりそれは、人生において重要であったり、有益な情報がキャッチできない、感知できない不利な状態ということです。
「勉強は人生に役立つ!」とだけ言われても実感しづらいですが、網の目を細かくすること=勉強と捉えるとどうでしょうか?
なるべく密な網で、色々キャッチしたいと思えますよね
「勉強が苦手」という意識が変化したから
この本を読むことで、日々感じ考え、知ることも勉強であり、私たちは毎日十分学んでいる勤勉な生物なんだということを知りました。
勉強ができない、取り組めない自分への後ろめたさや、勉強へのハードルが少し下がったように感じます。
ネットでの評判
最後に本書のネット上の評判、口コミを紹介します。
学ぶことに苦手意識がある人にこそ読んでほしい。『わかる』という感覚がどう生まれるのかが腑に落ちる本
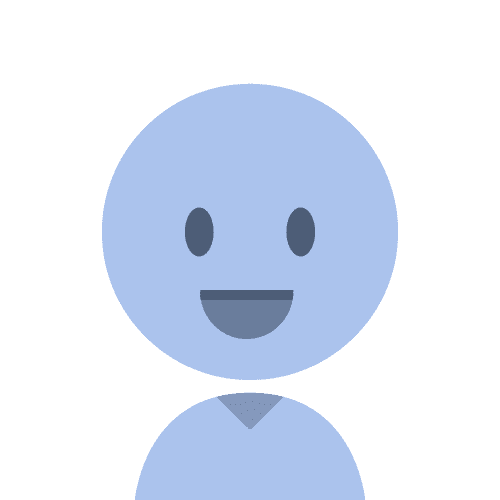
単に知識を覚えるのではなく、どうすれば本当に理解できるのかを脳科学の視点から説明してくれるのが面白い
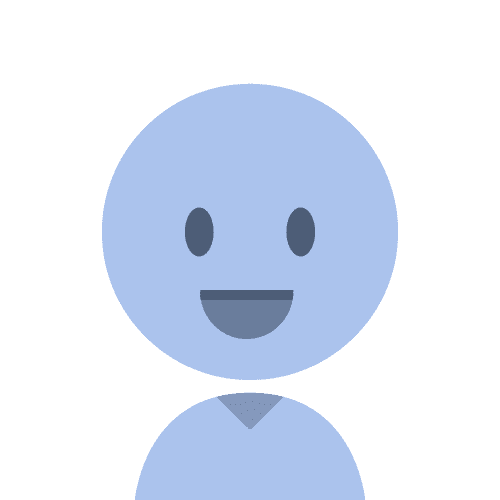
難しそうな内容だけど、例え話や具体的な説明が多く、意外と読みやすい
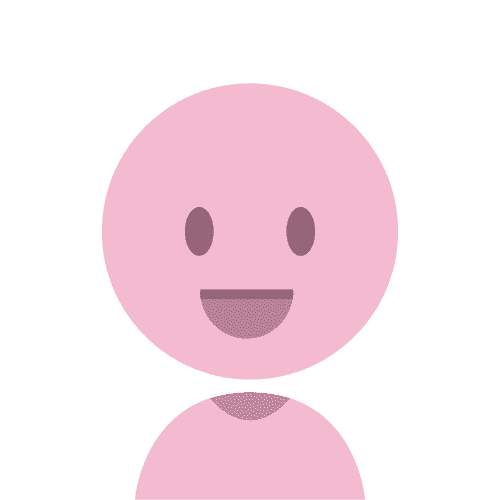
勉強が苦手な人でも、『わかる』を増やしていく方法が見つかるかも
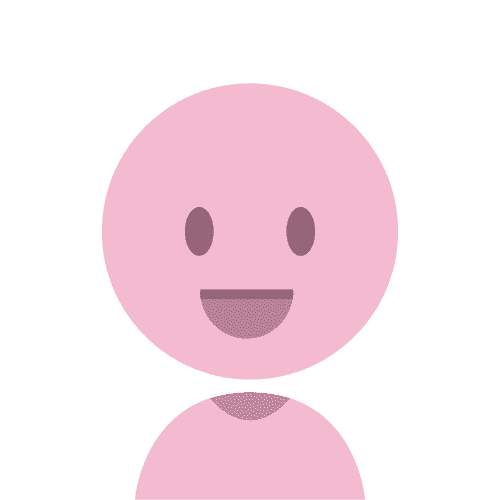
まとめ
『「わかる」とはどういうことか』は次のような方にぜひ読んでもらいたい1冊です。
- 現在学生の人
- 学ぶことに苦手意識がある人
- 勉強方法に迷っている人
- 大人になっても学び続けたい人
脳科学の視点から、イメージしやすい例を通して「わかる」という感覚を言語化し、解説しています。
「わかる」とはなんだろう?、勉強する意味はなんだろう?と疑問に感じた時、勉強のモチベーションを上げたい時、本書をめくってみてはいかがでしょうか。