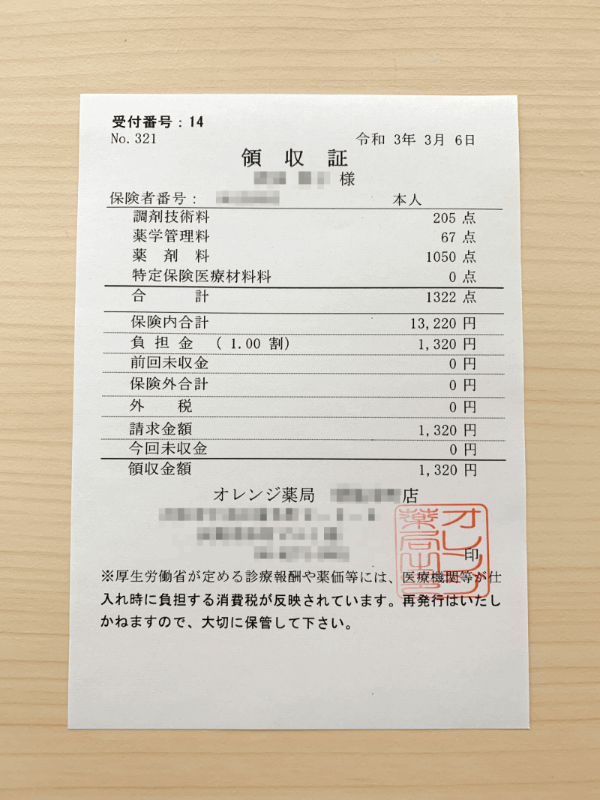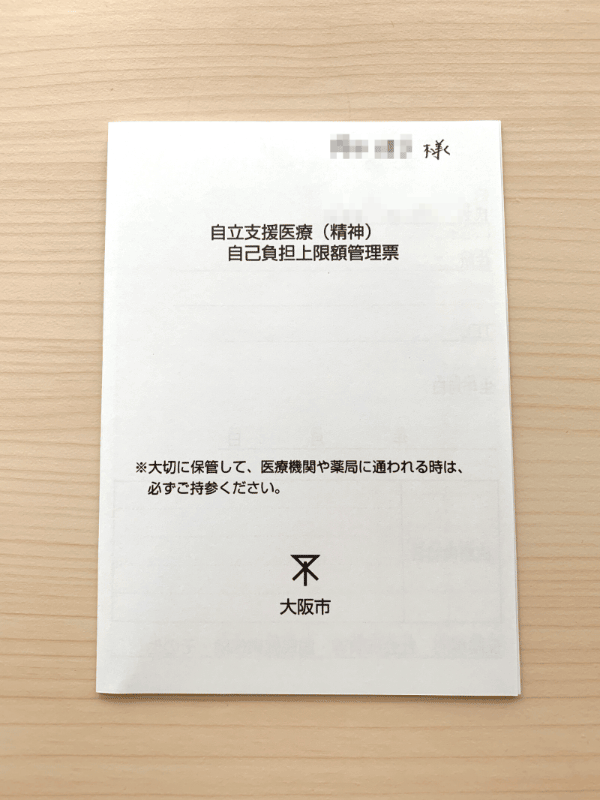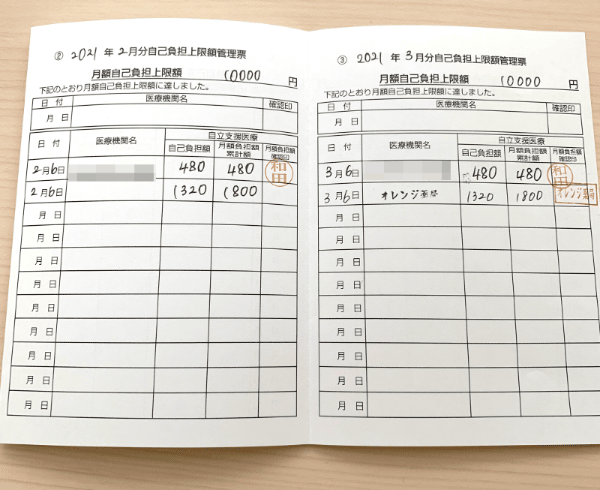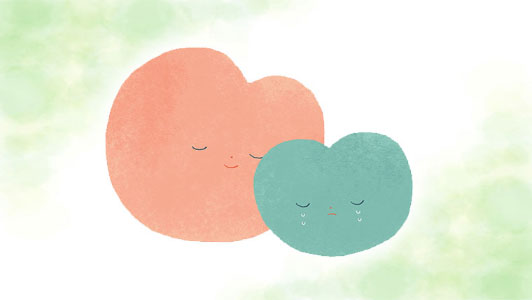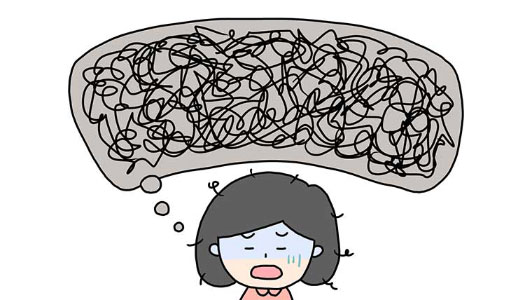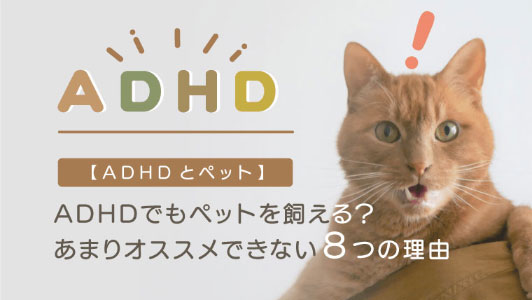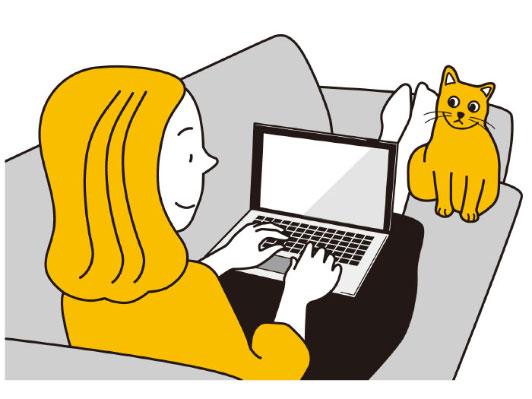【節約術】ADHD治療に使える「自立支援医療」とは?利用して医療費や薬代を安くしよう

こんにちは、むのです。
今回は「自立支援医療制度」の紹介と、私の実際の体験談についてお話しします。
以前の記事でも書きましたが、ADHDの治療には思った以上にお金がかかります。
通院は毎月必要で、場合によっては一生付き合うことになるため、費用の負担は無視できません。
この記事では以下の内容をまとめています。
- 自立支援医療制度とはどんな制度か
- 利用するとどれくらい負担が軽くなるのか
- 具体的な申請の流れと必要書類について
- 実際に使ってみて感じた注意点
制度を知らなかった方や、利用を検討している方はぜひ読んでみてください。
自立支援医療とは?
自立支援医療制度は、長期的な治療が必要な人の経済的負担を軽減するための制度です。
この制度には次の3つの種類があります。
- 精神通院医療(精神疾患の外来治療)
- 更生医療(身体障害のある方の治療)
- 育成医療(身体障害がある18歳未満の子どもの治療)
ADHDの治療は、このうちの「精神通院医療」に該当します。
対象となるのは、精神科や心療内科に入院せず、通院治療を継続している人です。
(通院・服薬・訪問看護・デイケアなど)
何がどのくらい安くなるの?
通常、医療費は3割自己負担ですが、自立支援医療を利用すると1割負担になります。
さらに、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されています。
たとえば、私のようにひとり暮らしで一定収入がある場合は、基本的に1割負担で済みます。
生活保護を受けている方は負担ゼロ、低所得者は、月額2,500円までの負担に抑えられるケースもあります。
具体的な金額区分は、お住まいの自治体のサイトや厚生労働省の資料で確認できます。
私の場合、これまで薬代は月4,000円ほどかかっていたのが、1,320円になりました(※2021年時点)。
診察代も1割負担になるため、月合計は5,000円→2,000円前後に下がりました。
3000円もお金が浮くのはかなり大きいです!
申請から利用までの流れ
申請から利用までは、以下のようなステップを踏みます。
- 主治医に自立支援医療の利用を相談する
- 市区町村の福祉窓口で申請書類をもらう
- 主治医に診断書など必要書類を記入してもらう
- マイナンバーカードなど必要な書類をそろえる
- 役所に必要書類を提出する
- 約2〜3か月後に病院へ証明書が届く
- 利用開始
まず主治医に相談を
ADHDの治療でも、すべての薬や治療法が制度対象になるわけではありません。
自分の治療が対象かどうか、最初に主治医に相談してみてください。
相談時に申請の流れを説明してくれる場合もあるので、聞いておくと安心です。
必要な書類を準備する
申請に必要な書類は自治体ごとに少し異なります。まずは役所の窓口で確認しながら書類を受け取ってください。
手数料がかかる書類もあるため、早めの準備がおすすめです。
役所に申請する
書類がそろったら、役所に申請します。
不明点は事前に電話で確認するか、窓口で聞きながら記入しても大丈夫です。
私も一部、わからない部分は空欄のまま窓口に持参し、その場で記入して受け取ってもらいました
証明書が届くまでの期間
証明書が届くまでは、2〜3か月程度かかります。私の場合、年末に申請したため、届いたのは翌年3月でした。
証明書は通院先の病院に送られ、医師や受付から渡されます。
利用時は証明書の提示が必要
証明書は「自己負担上限額管理票」という小冊子です。
地域によっては「受給者証」も発行されることがありますが、私は管理表のみが届き、それを利用しています。
利用できるのは、申請時に登録した医療機関や薬局に限られます。診察券や処方箋を出す際に、証明書も一緒に提出しましょう。
忘れると通常の自己負担になりますのでご注意ください。
証明書の中には、利用金額を記入する欄があり、病院と薬局側が記入してくれます。
正直な感想、ぺらぺらな紙なので無くしそう
紛失対策も忘れずに
この証明書は紙製で薄く、正直なところうっかり失くしそうです。私はお薬手帳のようなものを想像していたので驚きました。
心配な方は、パスポートケースなどに入れて管理するのがおすすめです。
初回利用時にさかのぼって返金されることも
申請時期によっては、疾患の診断書の日付にさかのぼって差額分が返金されるケースもあります。
私の場合も、主治医の診断書の日付以降の差額が戻ってきました。
これは申請時には聞いていなかったのですが、後から役所の方から電話で「いつから遡るか」を確認されて知りました。
自立支援医療の注意点
指定された医療機関・薬局でしか使えない
自立支援医療は、申請時に登録した「指定医療機関・薬局」でのみ利用できます。
申請時には、都道府県が指定する医療機関から、利用先をあらかじめ選ぶ必要があります。
引っ越しの多い方や、今後転居予定がある方は、事前に確認しておきましょう。近くに指定医療機関がない地域もあるので、注意が必要です。
利用には1年ごとの更新が必要
自立支援医療は1年ごとに更新が必要です。
更新を忘れると、一時的に通常の3割負担に戻ってしまいます。
ADHDの方はうっかり忘れがちなので、リマインダーなどで対策しておきましょう。
他の割引制度には使えない
この制度は、医療費の助成専用です。
障害者手帳のように、公共施設の割引や優遇措置には使えません。
まれに混同される方もいますが、行政サービスや交通機関の割引には非対応です。
勤務先に知られる心配はない?
私が不安だったのは、「申請すると会社に知られてしまうのでは?」という点でした。(※私はこの当時クローズ就労でした)
結論としては、勤務先に通知されることは一切ありません。
申請・利用は完全に個人の手続きであり、保険や年末調整にも影響はありません。
症状が軽くても申請していいの?
「軽い症状の自分が利用してもいいのだろうか?」と、私も最初は悩みました。
働くことすら難しい、もっと困っている人のための制度では?と思い、申請をためらっていたのです。
でも、現在困っていて通院している方なら、その時点で申請する権利があります。
迷っている方は、まず主治医に相談してみるのをおすすめします。
おわりに
ADHDは完治する病気ではなく、長く付き合っていく症状です。
制度を上手に活用して、少しでも生きやすい環境を整えていきましょう。
このブログでは他にもADHDに関する記事を書いています。