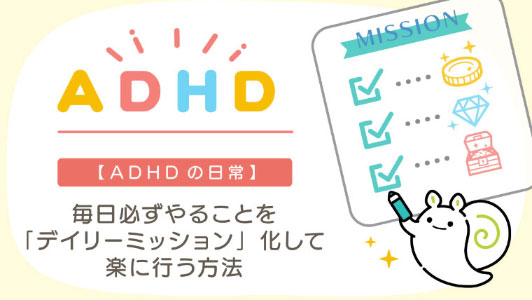発達障害やADHDでもペットを飼える?あまりオススメできない、8つの理由
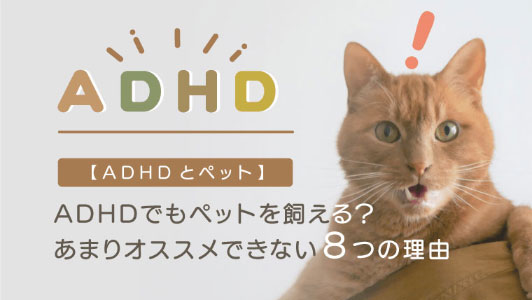
コロナ禍での巣ごもり生活をきっかけに、ペットを飼う人が増えました。
一方で、ペットの遺棄や保健所への持ち込みが増加しているとも報じられています。
多くの人が癒しを求めてペットを迎えるなか、ADHD当事者の中にも飼いたい方がいるのではないでしょうか。
そんな方には恐縮ですが、あらかじめお伝えしておきたい情報があります。
それは「ADHDの人がペットを飼うのをおすすめできない8つの理由」です。
発達障害はペットの世話ができない?
この記事がデメリット中心なのは、ADHDの私自身がペットを飼って困った経験が多かったからです。
また、他のADHDさんの「飼ってみたら違った…」という後悔を、できるだけ減らしたいと思って書いています。
もちろん、困りごとを上回る幸せもあります。
だからこそ、ペットと飼い主が幸せに暮らすために、ADHDとペット飼育の相性の悪い点も知っておいてほしいのです。
もし「今すぐ飼いたい!」という気持ちのある方がいれば、ぜひ体験談を参考にしてみてください。
ADHDの人がペットを飼うのをオススメできない、8つの理由
(1)自分にもペットにもお金がかかる
ADHDの人は、定型発達の人より日々の生活にお金がかかる傾向があります。
- 日々の家計
- 毎月の通院、薬代
- 無くしたものを再購入する費用
- 障害特性をカバーするための道具を買う費用
- (感覚過敏の人は)対応したアイテムなどを購入する費用
このような費用が余分にかかります。
そこにペットの飼育費用が加わると、家計はさらに圧迫されます。
ワクチン代や急な通院、ペット可の部屋の家賃など予想以上に費用がかさみます。
収入が十分であればよいのですが、そうでない方にとっては、かなり負担が大きくなることは明確です。
突然の出費の一例として「緊急入院や手術」があります。
私の経験では、1日で10万円が飛びました。保険に入っていてもです
(2)飽きっぽい性格だから
ADHDの人は熱しやすく冷めやすい傾向があります。
一方、数年〜十数年生きるペットの世話は、継続力が必要です。
子猫や子犬の時期は目に見える成長があり新鮮ですが、大人になると日々の世話は単調になります。
「毎日同じこと」の繰り返しが苦手なADHDは、途中で飽きるリスクや、他のペットに興味が移る可能性があります。
自分はそういうことがありそう…と少しでも思った方は、一度立ち止まって考えてみてください。
(3)長期計画を立てるのが苦手だから
ペットによっては数十年と非常に長生きする種類もいます。
1年後すら見通すのが難しいADHDの人にとっては、この長さの飼育計画を考えることはかなり難しいと思います。
転職や結婚、子育てなど環境が変わることや、ペットの介護が必要になることもあります。
ペットが飼えない場所に引っ越す可能性もあるでしょう。
そのときに託せる人がいるか、長期的に飼えるか、しっかり考えてから迎えましょう。
ライフプランなしに、衝動に任せて飼うことは危険です。
ペットも高齢になると介護が発生します。これを考えていない人は多いのではないでしょうか?私もそのひとりでした
(4)お世話を忘れたり先延ばししやすいから

ADHDのうっかり忘れと先延ばしがペットの世話で起こると危険です。
「ご飯をあげたつもりであげていなかった」などのミスが起きやすいのがADHDです。
掃除や予防接種なども、つい先延ばしにしてしまうことがあります。
このような小さなミスが積み重なり、ペットの健康を損なうことにもなりかねません。
(5)睡眠不足により特性が悪化するから

ハムスターや猫など、夜行性のペットは深夜や早朝に活発に動くことがあります。
ペットの性格やしつけの仕方によっては、要求鳴きという行動を取ることもあります。
これは、夜中に鳴き続けることで飼い主を起こし、ご飯をねだる、遊んでもらいたがるといった行動のことです。
これらの騒音問題は、ただでさえ睡眠トラブルが多いADHDの人には、大きなストレスになります。
私もこの問題に悩まされていた時期がありました。
深夜3時ごろ猫に起こされ、遊んだりおやつをあげたりし、そのまま起きっぱなしで仕事に行くのです。
当然頭はぼんやり、ミスも多い1日を過ごすことになります
(6)集中力を削がれるから
室内でペットを自由にさせている場合、仕事や勉強中に構ってほしがるペットに注意が向いてしまうことがあります。
部屋を分けられない環境だと、集中するのが難しくなるでしょう。
自分の特性と照らし合わせ、生活に支障が出ないかを見極める必要があります。
(7)部屋が散らかりやすくなるから
ADHDの人には片付けが苦手な方が多くいます。
ひどいと汚部屋と呼ばれる状態になってしまう方もいますよね。
部屋が散らかるとペットの誤飲事故など、命に関わる問題も出てきます。
さらに、ペットがいると抜け毛や粗相、色々なもので部屋が汚れるスピードが早いです。
日々の掃除が追いつかず、ペットと人間双方の病気の原因になることもあります。
(8)多頭飼育崩壊につながる恐れがあるから

「多頭飼育崩壊」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
ペットを世話しきれない数まで増やしてしまい、人間の生活ができなくなる。
ペットが世話されず病気になったり、亡くなってしまうという状況です。
なんらかの精神疾患・障害などを抱えた人が起こしやすいと言われています。その中には発達障害も含まれます。
飼い始めた時は問題がなくても、あとから二次障害の精神疾患が出てしまう。
体調不良になった時お世話ができなくなる、という可能性がADHDの人は高いです。
一人暮らしのADHD当事者の場合、キャパシティを超えやすいため、特に注意が必要です。
それでも飼いたいという人へ
ここまでの内容を読んで「やっぱり無理そう」と思った方もいれば、「行けそう!」と感じた方もいると思います。
ここからは、デメリットを理解したうえでペットを飼う際の工夫について紹介します。
やはり飼えないと思ったら、動物施設を活用しよう

ADHDの人にとって難しいのは、日々の細かな世話を継続することです。
その負担を避けながら動物と触れ合う方法として、施設の利用があります。
猫カフェや犬カフェ、動物のいる宿などを活用すれば、お世話の負担なしで癒しの時間を体験できます。
施設利用の費用は、ペットを一生飼う費用に比べても格段に安く済みます。
「飼わないことも愛情」といった言葉があるように、自分の手で飼育しなくても動物と関わる手段はたくさんあります。
家族で協力して飼う
家族がいる場合は、世話の分担によって負担を大きく減らすことができます。
何かあった時に助け合える体制があるのは大きな安心材料です。
一人で飼い始める方も、いざという時に引き継いでくれる人がいれば安心です。
家族と話し合い、事前に役割や協力体制を決めておきましょう。
常時8,000アイテム以上掲載!
ペット用品・ペットグッズは【犬・猫の総合情報サイト『PEPPY(ペピイ)』】![]()
意思表示できる動物を選ぶ

犬や猫、鳥、ウサギなど、異常時に意思表示をしてくれる動物がおすすめです。
鳴いたり動いたりすることで、飼い主が気づける場面が増えます。
一方で、爬虫類や水棲生物などは体調の変化に気づきにくく、観察に注意力を要するため、ADHDの人には難しい面があります。
我が家の猫は、ご飯やトイレのタイミングで鳴いて知らせてくれるので助かっています
飼うと決めたら「覚悟」と「計画性」を
私はADHDの診断前にペットを迎えました。その結果、準備不足で後悔することも多くありました。
しつけを甘くした結果、要求鳴きがひどくなったり、仕事で帰宅が遅れて長時間留守番をさせてしまったこともあります。
現在は無職で、収入面でも不安がありました。(※記事執筆時点:2025年現在はフリーランス)
そのような状況もあり、自分とペットのライフステージを重ねた計画表を作成しました。
自分が何歳の時にペットが何歳か、今後何が起こり得るかを予測した計画表です。
場当たり的な対応を減らし、事前に備えることで負担はぐっと減ります。作ってみて損はないと思いますよ。
おわりに
ここまで「飼わない方がよい理由」を書いてきましたが、決して「飼ってはいけない」というわけではありません。
ADHDがあってもペットを飼うことは可能ですし、ちゃんとお世話もできます。
最初の頃はうっかりミスもありましたが、命を前にすると自然と責任感が芽生え、いつの間にかお世話も習慣になっていました。
また、人間が抜けている分、ペットの方がリードしてくれる場面も多いです。
結局のところ、大切なのは障害の有無ではなく、その人が持つペットへの愛情と責任感だと私は感じています。
ADHDの人は衝動的に飼うのではなく、自分の特性や生活を見つめ直したうえで、最後までお世話できると判断できた時にぜひ迎えてあげてください。
以上、ADHDの人がペットを飼うのはおすすめできない8つの理由でした。
このブログでは他にもペットに関する記事を書いています。