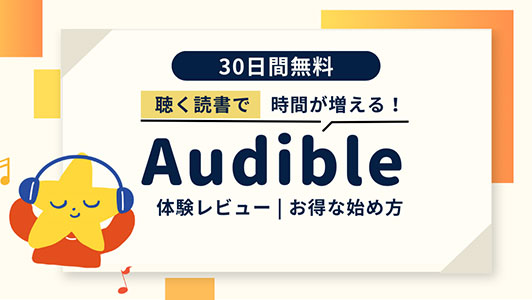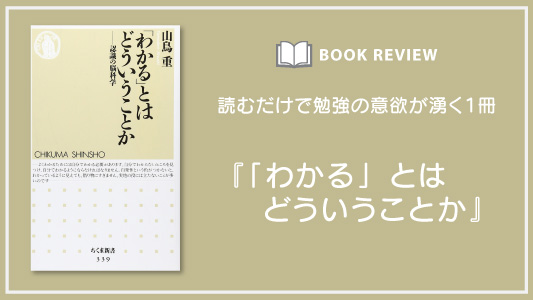生成AIの話題が苦手な人・生成AI初心者でも読みやすい『ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本』
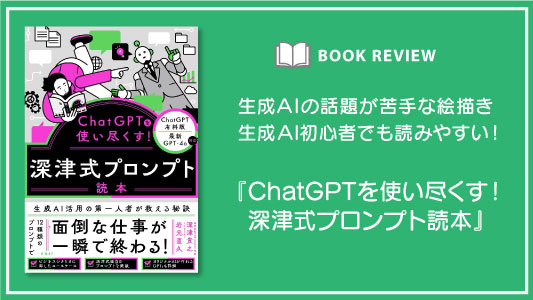
〔前略〕ITの話題だけでなく、暮らしやビジネスの今や将来を語るときにも、ChatGPTや生成AIというキーワードが多く含まれるようになってきています。すでにChatGPTのある世界に生きている私たちは、なかった世界に戻ることは不可能なのです。〔後略〕
引用:ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本 p.003 まえがき
こんにちは、むのです。
この記事では、生成AIに苦手意識のある方や生成AI初心者の方が、生成AIを学び始めるのにベストな1冊を紹介します。
筆者は一時期、生成AIへの反発感が強くなりすぎてAIの2文字すら見たくない!という状態に陥っていました。
そんな時でも最後まで読むことができ、生成AIの基本知識を学べたのがこの本、『ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本』です。
生成AIのことをこれから知ろうという方が出会う最初の1冊として内容のバランスが最適だと感じました
この記事が生成AIに触れるはじめの一歩のお手伝いになれば幸いです。
ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本:概要
著者紹介
ITジャーナリスト/ライター。慶應義塾大学理工学部卒業、同大学院修士課程修了。日経BPでIT、PCを中心にした雑誌、Web媒体で記者・副編集長を歴任。独立後は雑誌書籍などを幅広く執筆する。
本の簡単な内容
この本では、ChatGPTを主題に生成AIの基本的な性質や使い方から、ビジネスシーンにおける活用法までを優しくわかりやすく紹介しています。
生成AIとはどういったものか?何が得意で何が苦手なのか?どのように命令すれば欲しい回答を出してくれるのか?
そのテクニックを「深津式プロンプト」として実例を上げながら解説。
また、生成AIのリスクや著作権問題、知っておくべきガイドラインの紹介など、他のAI指南本があまり触れない部分にもしっかりとスポットが当てられています。
本の目次紹介
- 第1章 はじめに:ChatGPTに触れてみよう
- 第2章 ChatGPTと生成AIの基本理解
- 第3章 ビジネスシナリオでのChatGPT(基礎)
- 第4章 プロンプトの力を引き出す
- 第5章 ビジネスシナリオでのChatGPT
- 第6章 カスタマイズしたChatGPTを作る
- 第7章 リスクの認識と管理
- 第8章 組織での活用とさらなる応用
この本をおすすめする理由
著者がデザイナーだから
私はデザイン勉強のため、著者:深津さんのXアカウントを6年以上フォローしています。
そこで、生成AI登場時からデザイナーとして可能性と問題点の両方に言及していた様子を見てきたため、本の内容への信用度が高いです。
- 著者が推進派・慎重派どちらの意見も認識したうえでバランスの良い考え方をしている
- 生成AIに対するクリエイターの心情を逆撫でするような表現が使われていない
すぐに役立つ用法がたくさん載っているから
読みながらすぐに使える、便利な用法がたくさん載っているのもおすすめ理由です。
専門的な知識がなくても、本の通りに入力すれば同じような結果を得ることが出来ます。
生成AIに対して冷静に向き合えるようになるから
生成AIによって生活が脅かされる、新たな問題が起きるといった不安感から構えてしまう人も多いのではと思います。私もその1人です。
しかし、この本でAI技術の基本知識や特性を学んだことで、漠然とした不安感・苦手感が和らいだと感じます。
特に、仕事がAIと競合しそうで不安の大きい方は読んでみて欲しいです。
生成AIと人力それぞれの強みを改めて認識することができ、補助ツールとして共存する未来を見いだせます。
この本で得られた有益な知識3選
ここからは、この本から得られた有益と感じた知識を3つ紹介します。
生成AIの本質は「確率で続きを書く機械」である
本書で深津さんは、ChatGPTについて「確率で続きを書く機械であることを忘れないようにしてください」と述べています。
これは、ChatGPTなどが出力する文章や生成物は人間の入力した文章(命令)に対する予測結果であり、AIが0から創造した物ではないためです。
ですから、実はあり得そうな答えが出力されるだけで100%それが正しいという保証はないのです。
AIの脳とも言える大規模言語モデルは、インターネット中などから大量の情報を集め、さらに不適切なことを出力しないよう人間がトレーニングを加えています。
ネットですでに人々が間違っている情報、バイアスがかった情報はそのまま学習されている可能性がある。これが生成AIの本質です。
AIは何でも答えを出してくれる、クリーンで正確性が高い!という認識が改まりました。
あくまでもAIは機械で、人の知識がまだまだ必要です
ChatGPTが得意なこと・不得意なこと
生成AIやChatGPTは何ができて何ができないのか、知っておくことで適切な使い所を選択できます。
得意なこと
- 一般論。誰に聞いても答えられる質問への回答
- 前例やパターンのある判断
- あたえられたデータをまとめる作業
- プログラミング支援
不得意なこと
- 皆が言わなそうな独特なアイディア
- クリエイティブな発想
- 誰も知らない・存在しない物事への回答
- 例外的な判断
- 倫理的・感情的な判断
- 数学的な計算
- リアルタイム情報の提供
ハルシネーション(幻覚)を作り出す問題
生成AIは「誰も知らない物事」「存在しない物事」を聞かれたとき、ハルシネーションという状況を起こす場合があるそうです。
これは、「そういった質問にはこういう答えが続くかな?」と、AIが勝手に予測して実在しない説明や解説をしてしまうことです。
架空の研究結果や歴史的事実などをそれらしく回答してしまうため、誤情報やデマを作り出す問題となっています。
生成AIの得意・不得意なことを知ると、全てをAIに置き換えることはまだ先になりそうな印象
ChatGPTを使った仕事の効率化事例
この本では、以下のようなビジネスシーンでの使い方を、実際のプロンプト例と一緒に紹介しています。
- 与えた資料を元にレポートや企画書を作成する
- キャッチコピーなどの複数パターンを一気に作成する
- レポートなど長い文章の内容を簡潔にまとめる
- 文章校正をする
- 検索して結果をまとめる
- エクセルデータなどから図表を作る
- 複数の手段を検討&結果を予測してもらう
- タスクに必要な行動と理由を考えてもらう
どれも人力で行うには少し面倒な作業ですよね。
画像生成のような機能にはまだ抵抗感がありますが、こういった雑務を高速処理してくれる能力は頼ってみたいと感じました。
文章校正はメールやブログでも使えますね。
「タスクに必要な行動と理由を考える」という使い方は、計画が苦手なADHDさんのサポートにも良さそうです
まとめ
『ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本』は次のような方におすすめの1冊です。
- 生成AIに苦手意識がある人
- 生成AIを避けがちな絵描き、クリエイター
- これから生成AIを学ぶ人
- ChatGPTを学び始めたい人
デザイン・ITに詳しい著者二人が、優しく分かりやすい例を用いながら、生成AIの有用性・問題点をバランスよく解説しています。
まだ法整備が整っていないこの技術と付き合っていくためにも、本書で学び始めてみてはいかがでしょうか?
このブログでは他にも生成AIに関する記事を書いています。