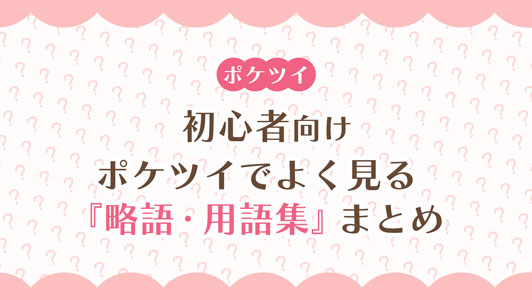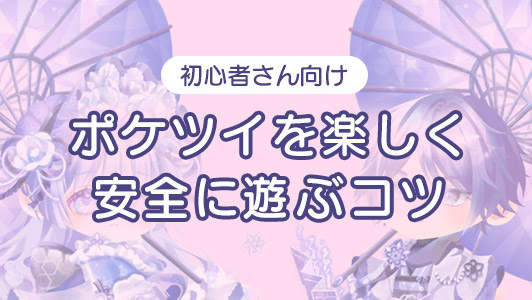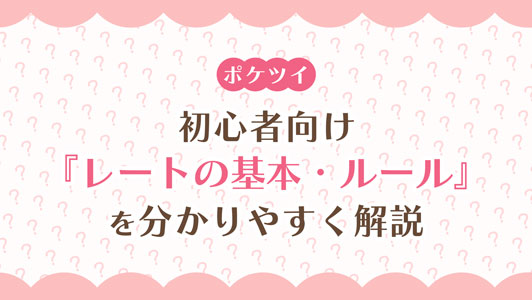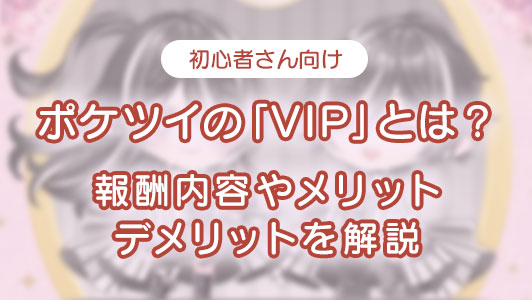最近「推し疲れ」していませんか?推し活を無理なく楽しく続けるコツ3選

学生から社会人まで幅広い世代に浸透し、いまや国民的な趣味となっている「推し活」。
しかし、その一方で、流行や推し活自体に疲れを感じている人も少なくありません。
楽しいはずの趣味が辛くなってしまうのはなぜでしょうか? どうすれば無理なく推し活を楽しみ続けることができるのでしょうか?
この記事では、推し活を無理なく楽しく続けるための3つのコツを紹介します。
エンタメ業界での勤務経験もある筆者が、提供者側とファン側、両方の視点を交えながら解説していきます
「推し活」と「推し疲れ」とは?
「推し活」はどんなことをするの?
はじめに、「推し活」とはどんな活動を指すのでしょうか?
ジャンルや界隈によってさまざまな形がありますが、一般的には以下のような活動の総称です。
- ライブやイベントに参加する
- 推しの出演する番組や配信を視聴する
- SNSや雑誌で推しの情報をチェックする
- グッズやCDを購入する
- ファンアートや二次創作を制作する
- 推しを布教する
- 直接投げ銭をする(配信者など)
このように、ファン自身も楽しみながら、お金や時間をかけて推しを応援する活動を「推し活」といいます
「推し疲れ」とはどういう状態?
楽しくてつい夢中になってしまう推し活ですが、のめり込みすぎることで心や体に負担を感じる状態を「推し疲れ」と呼びます。
例えば、以下のような状況に心当たりはありませんか?
- 「推しにお金をかけすぎてしまった」
- 「常に最新情報を追いかけていて、気が休まらない」
- 「周囲のファンと比べてしまい、焦りを感じる」
- 「応援することが義務のように感じるようになった」
- 「以前ほど推しに熱量を注げなくなった気がする」
本来は楽しいはずの推し活が、知らないうちに負担になってしまうことも…。
推し活で疲れてしまう主な原因
推し疲れの原因は人それぞれですが、よくあるものをいくつか紹介します。
経済的な負担
グッズやチケット、イベント参加費など、推し活にはお金がかかります。
無理をしてまで出費を続けると、生活や気持ちの余裕がなくなり、推し活が楽しめない状態になってしまいます。
「気持ちよくお金を出せない」「グッズ購入に悩む」「お金の工面に困る」といった兆候がある場合は要注意!
自分の経済的なキャパシティを超えて無理な出費をしている可能性があります
情報収集に追われる
推しの最新情報を見逃さないようにSNSを常にチェックしていると、気が休まりません。「トレンドに乗らなきゃ!」と焦る気持ちも、推し疲れの原因になります。
なぜなら、「幸せな情報であっても、脳にとってはストレスになる」からです。
刺激的な情報や不安を煽るデマ、ファン同士の熱い議論に刺激を受け続けると、脳が「脳疲労」を起こし、興味や関心を失う状態になることもあります。
ゴシップ好きなファンには注意
推し活をしていると、SNSでファン同士つながりたいと思うこともありますよね。
しかし、中には「噂好きなファン」も存在します。
こうしたファンは、真偽不明の情報や見たくない・知りたくない情報を拡散しがちで、推し活のストレス要因になりやすいです。
周囲のファンとの比較
「あの人はたくさん遠征してるのに、私は行けない」「買えるグッズの数が少ない…」「◯◯しない人はファンじゃないと言われた…」と、他人と比べて落ち込んでしまうこともありますよね。
しかし、推し活は誰かと競うものではありません。
時間の使い方も、使えるお金も、住んでいる場所も、ファン一人ひとり条件が異なります。
「他の人と同じように推し活しなきゃ!」と無理をすると、いつか燃え尽きてしまうかもしれません。
本来、「推し活」とは「自分と推しの間にある応援活動」です。
周囲にマウントを取る人は、推し活の本質を履き違えているかもしれません。気にせず、自分のペースで楽しみましょう。
「推し」にのめり込みすぎる「パラソーシャル関係」
推しに対して強い思い入れを持ちすぎて、必要以上に疲れてしまうことも推し疲れの原因になります。
例えば、
- 推しの発言の意味や背景が気になりすぎる
- 推しのプライベートのことまで考え込んでしまう
- 「私が支えなきゃ」「グッズを買わなきゃ」と推しの仕事を心配しすぎる
- 推しへの評判や批判が気になり、ついチェックしてしまう
このように、推しとファン以上の関係性を感じ始めたら、パラソーシャル関係に陥っている可能性があります。
推しは多くの場合、ファンよりも立場も生活も安定しています。
心配しすぎず、娯楽のひとつとして、推しが提供してくれる楽しさを素直に受け取りましょう
提供する企業側に原因がある場合も
「推し活」を一つの商機としてブーム化し、消費を促す企業活動が「推し疲れ」の原因になることもあります。
なんでも「推し活」につなげる
- 推しとのコラボ案件やコラボ商品の展開
- メンバーカラーを意識したグッズの販売
- 推しとの接点を作ることで自社商品のアピール
商業戦略としては正しい活動ですが、消費者側からするとプレッシャーを感じることもあります。
特にコラボ商品は気になってしまいますよね。
また出た!うれしい!でももう買えないよ!という悲鳴を、筆者もよく上げています…。
推しの宣伝によって商品が売れた実績が次の仕事につながることをファンも理解しているため、少なからず購入のプレッシャーを感じることも…
「ランダム商法」「くじ商品」を出す
推しグッズを手に入れるために余分なお金を払わせる、「ランダム商法」「くじ商品」は、確実に消費者の購買意欲を削ぎます。
ガチャと同じく利益率が高いため、企業が採用しがちな手法ですが、ファンにとっては悩ましい問題です。
欲しいグッズだけを買えない虚しさ、無力感が積み重なると、グッズ自体もういらないと感じてしまうこともあります。
ファンを飽きさせないように情報やイベントを詰め込む
現代は情報の消費速度が非常に速く、バズった話題も数日で忘れられてしまいます。
その中で、推しや自社商品を忘れさせないために、企業は情報発信やイベント提供を続けなければなりません。
しかし、過剰に詰め込みすぎると、ファンのキャパシティを超え、推し疲れの原因になってしまうこともあります。
企業側も「どうすればファンが喜ぶのか」を日々考えていますが、ファンの負担にならないバランスも大切ですね
無理なく楽しく推し活を続けるコツ3選
上記のような問題にとらわれず、楽しく推し活を続けるためには、以下のようなことを心がけるとよいでしょう。
1. マイペースを大切にする
推し活は「自分が楽しむこと」が第一です。
あくまでも趣味のひとつなのですから、無理せず自分のペースで応援しましょう。
推し活をする時間を決めたり、無理のない範囲で課金したりすることが大切です。
時には「ここで盛り上げなければ!」という場面も訪れますが、推し達が本当に喜ぶのは「長く応援してくれる・楽しんでくれるファン」の存在です。
そのことを忘れないようにしましょう。
2. 推し活デトックスを取り入れる
「なんとなく推し活に疲れたな…」と感じたら、一度距離を置くのも効果的です。
推し情報やコンテンツを見ない日を作ったり、推し活以外の趣味や友達との時間を大切にすることで、気分をリフレッシュできます。
心に余裕ができると、また楽しく推し活を再開できますよ。
3. 「推しがいる幸せ」を思い出す
推し活がつらく感じたときは、「どうして推しを好きになったのか?」「応援することで自分が得ているもの」を思い出してみてください。
- あのライブで一目惚れしたんだよね
- 推しの笑顔に癒やされてる
- 元気な歌声を聞くと仕事を頑張れる
- あの時の推しの言葉が勇気をくれた
- 自分の青春の思い出!
このように、推しのパフォーマンスに心を動かされた瞬間を振り返ることで、初心に戻ることができます。
まとめ
推し活は楽しいものですが、頑張りすぎると「推し疲れ」してしまうこともあります。
そんなときは、マイペースを第一に、無理なく応援する方法を見つけてみましょう。
ここまで読んでくださった皆さんの推し活が、より良いものになりますように。