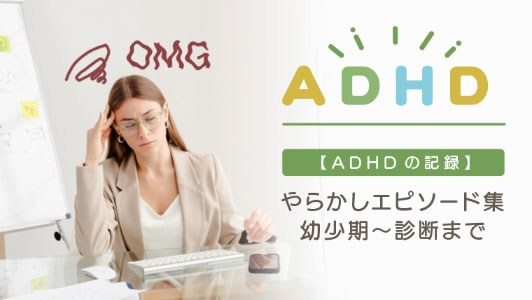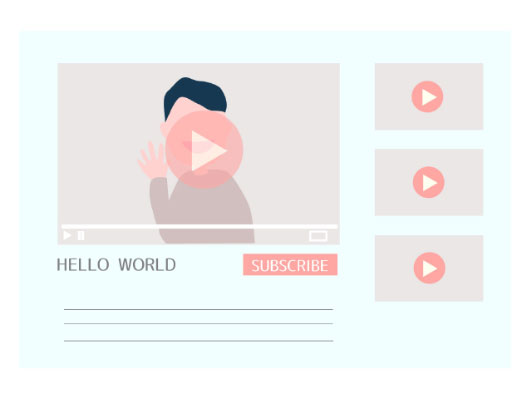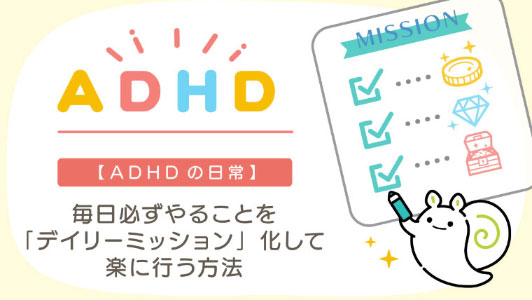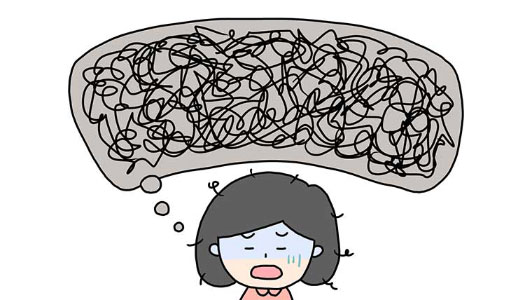【体験談あり】ASD(自閉スペクトラム症)を持つ人が父親になると子どもや家族に与える影響

こんにちは、むのです。
この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)を持つ男性が父親になった場合、子どもや家族にどのような影響を及ぼすのか、一般的な情報や体験談等をまとめました。
なぜこの記事を書いたのかというと、最近ASD男性と結婚した友人から困りごとの相談を受けることが増えたからです。
- ASDのある父親の特徴
- 彼らの子供や家族との関わり方
- どんな影響や問題が起こるのか
こういった疑問のある方や、ASD当事者の方に、周りを見直すきっかけとして読んでいただければ幸いです。
ASD特性を持つ父親の特徴
一般的に、ASDの父親には以下のような特徴が見られると言われています。
コミュニケーションが苦手
- 家族の気持ちを察することが難しい
- 会話が一方的になりやすい
- 決めつけにより相手の意図を誤解することがある
- 自分と異なる家族の意見を強く否定する
- 意見のすり合わせや相談が苦手
- 家族会議などが嫌い
- 自分の非を認めず謝らない
自分ルールを重視する
- 日々の決まった習慣やルールを守ることを好む
- 急な予定変更が苦手
- 臨機応変な対応が苦手
感情表現が不得意
- 喜びや悲しみといった感情をあまり表に出さない
- 家族と感情を共有することが苦手
- 家族に「何を考えているのかわからない」と言われることがある
- パニックになったり、気に入らない事があると癇癪を起こす
- 不機嫌や怒りで周りをコントロールする
特定の興味に没頭する
- 特定の趣味や仕事に強いこだわりを持つ
- 関心が家庭以外に向くと、家族との関係が希薄になる
- 子育てより自分の興味に集中しやすい
感覚過敏または鈍麻
- 音や光、匂いに敏感
- 逆に鈍感な場合もある
- 他の家族の出す生活音を気にする
- 子どもの泣き声に強い不快感を示すか、無関心
外で見せる顔と家族に見せる顔が違う
- 外では優秀な人間のイメージがある
- 外では人付き合いも問題なくできる
- 家庭内では家族をぞんざいに扱う
- モラハラ気質を持つ
- 暴力は振るわないことが多い(世間体を気にする)
父親がASDだった場合子どもに起こる影響
ASDの父親を持つ子どもは、以下のような影響を受けることがあります。
程よい人間関係を学べない
- ASD特有の話し方に慣れてしまうことで、友人など他者との会話でそれを再現してしまい、苦労することがある
- 父親独自のルールを他者にも押し付けてしまうことがある
- 一般的なコミュニケーションパターンを身につけ辛い
人間関係の最小単位は家族だといわれます。
その家庭内で、ASD対応に特化したコミュニケーションに慣れてしまうと、一般的なコミュニケーションに対応できなくなることがあります。
共感や感情表現を学びにくい
- 父親の共感、承認不足から心が弱くなる
- 他者への共感が薄くなる
- 自信が持てなくなる
- 自己肯定感が低くなる
- 父親の感情表現をロールモデルとしてしまい、癇癪や自傷を起こす
父親が感情表現をあまりしない場合、子どもも感情の表現方法を学びにくくなることがあります。
家族になにかしてもらった時の感謝、食事に対する美味しいといった感動表現などが乏しくなります。
ルールや秩序を重視する傾向が強まる
- 子どものこだわりも強くなる
- 父親から強い抑制を受けることで、子どももルールや秩序を重要視するようになる
- 変化に対して過度に不安を感じるようになる
父親の影響から子ども自身も強いこだわりを持つようになると、社会との接点を柔軟に築けなくなる可能性があります。
精神疾患になる
- 父親の特性に適応できずパニックを起こす
- 逆に過剰適応を起こす
- 健全な愛着が育たない
- 定型発達児でも発達障害のような特性を示すようになる
- 強いコンプレックスを抱く
- 無気力になる
- うつのような状態になる
大人でも対応が難しいASD特性に対し、子どもは混乱し、傷つきながらなんとか適応しようとします。
その過程や積み重ねの結果、精神疾患を発症する可能性も高いと言われています。
父親がASDだった場合家族に起こる影響
ASDの父親がいる家庭では、以下のような問題が生じることがあります。
夫婦間のコミュニケーション不和
- 夫婦間の意思疎通が難しい
- すれ違いや誤解が生じやすくなる
- 話し合いの場を作れない
- 上記の積み重ねから夫婦喧嘩や離婚なども起きやすい
子育ての負担が偏る
- 父親が育児に関心を持たない場合、全て母親任せになる
- 夫婦で協力して子育てができない
- 子どもの責任は母親の責任、など極端な思考を持ちやすい
- 母親が父親を頼ることができず、負担やストレスが増大する
ASD特性のある男性と暮らす女性からよく聞かれるのが、「子どもを2人育てている感じ」という言葉です。
そのくらい、負担が片方に偏ってしまう可能性が高くなります。
家庭内の雰囲気が冷たくなる
- 夫婦間で感情の共有ができない
- 家族全体が無機質な関係になりやすい
- 諍いや無視などが起きやすい
- 両親を見て子どもが萎縮する、または荒れてしまう
突発的な問題への対応が難しい
- 話し合いが苦手な父親の場合、問題へ向き合わないため解決ができない
- 臨機応変な対応をして貰えない、できない
ASD当事者、またはそうではない家族が精神疾患になる
- 家族がいわゆるカサンドラ症候群のような状態を起こす可能性がある
- ASD当事者にも強い負荷がかかり、うつなどの疾患を引き起こす可能性がある
筆者と友人達のASD父親体験談
ここまでは、一般的なASD特性を持つ父親の特徴をまとめました。
この特性に本人の性格や生育環境などが加わると、笑えない話がいくつも生まれます。
以下に、実際に私や友人達が体験したASD持ち父親の話をご紹介します。
計画は曲げない!0⇔100思考の塊
親戚と計画していたキャンプに台風が直撃。延期しようという声が挙がりましたが、父は「予定通りにやる!」の一点張り。
結局親戚は辞退し、むの一家だけが嵐のキャンプ場へ出発。
暴風の中ずぶ濡れになり、暴言を吐きながらテントを立てる父親をなだめるはめになりました。
家族サービスとして自分が食事を作る!と台所に立った父親ですが、フライパン返しに失敗し、食材を床にぶちまけてしまいました。
その瞬間、癇癪を起こしてフライパンごと料理をゴミ箱にシュート。そして、大声で悪態をつき、わざと大きな音を立てながら再度調理を開始。
今度は完成しましたが、ゴミ箱の残骸と不機嫌な父親を横目に素直に料理を味わう気持ちにはなれませんでした…。
家族で出かける時は、全ての行程と時間をきっちり決めないと気が済まない父。
予期せぬトラブルで一つでも予定が狂うと、もう不機嫌が止まらない。原因が家族にあった場合は、帰宅後までずっと文句を言い続けます。
なんのための家族旅行なんでしょうか?

自分中心すぎる!家族のことを考えて
少しでも自分のこだわりに合わないと、家族に相談せずにすぐ仕事をやめてしまう夫。そして、反省を活かさず気分で次の仕事を決めてしまう。
そんななので職場も給与も安定せず、家計が苦しいのに、趣味のゲーム機やパソコンなどはポンポン買ってくる。
共働きなので生活はできているが、怒っても何が悪いのか理解していないみたい…子どももいるのに…。

私が他県で一人暮らし中、母親がひどく体調を崩し寝込んだ日があった。
母一人では動けなかったので、同居していた父に看病をお願いしたが、何もせず釣りに出かけていた。
後で怒って問い詰めると、「看病の方法を知らなかった」「母に聞いたら大丈夫と言っていたので出かけた。俺が悪いのか?!」と逆ギレ。
これでも企業の役員なのに…家では家族の世話もできないASD父親です。
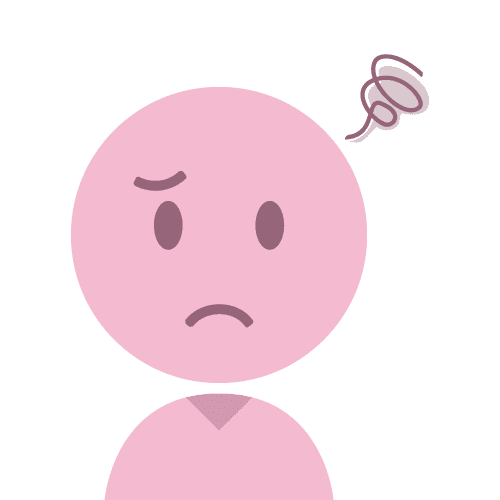
人の気持ちが分からない?心が折れた…
小学生の頃、父が遊びに連れて行ってくれた場所は、電車の撮影や鉄道模型のイベントばかり。
女の私はショッピングやディズニーに行きたかったのに、そういった場所には一度も連れて行ってくれなかった。
子どもの好みや趣味を知らない、興味すらない。自分の趣味に付き合わせるのが家族サービスだと本気で思っていたようです。
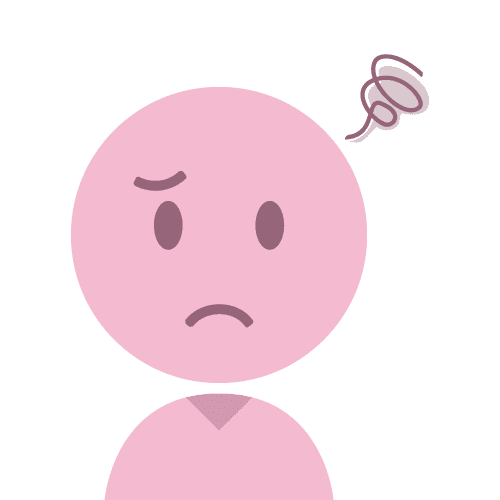
学生の時、通学路で不審者に追いかけられた事があった。
帰宅後に父親に相談すると、「気のせいだろう」「お前に興味を持つ男はいない」と言われた上、「話がしつこい、今忙しいから」など興味なさげにあしらわれた。
怖かった・不安だったという気持ちをわかって貰えず、それからは何も相談しないようになった。
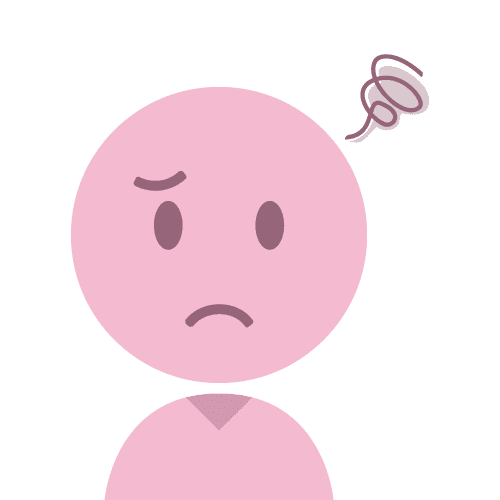
普通の家庭のように、父の日や誕生日には贈り物をしていましたが、喜ばれなかったり横流しをされました。
ある時、子どもながらに気を遣って、父がよく使う文房具をプレゼントしたところ、「これは経費で買うから必要ない。返品してきなさい」と突き返されました。
またある時は、父に似合いそうなセーターを選んでプレゼントしたところ、好みではないからと隣りにいた祖母に与えていました。
相手がどう思うのか考えることができない、これを平気でするのがASD持ちです…。
実家が裕福だったり、長男のASD持ちは問題を起こしやすい?
ここで紹介した筆者や友人の父は、ほとんどが長男で実家が太く、不自由のない生活を送ってきたASD当事者でした。
さらに、昭和の家父長制を重んじた長男信仰も相まってか、ASDの良くない部分を指摘されずに育ったのではと感じます。
おわりに
以上が、ASDを持つ人が父親になると子供や家族に起きる影響と体験談のまとめでした。
ASDについて悪いことばかり書いて!と、不快に思われる方は勿論いらっしゃると思いますが、ここにまとめられる程度の実例と体験が身の回りに溢れているのも事実です。
しかし、周りが根気よく諭したり、ASD当事者が自己理解を深め、適切なサポートを受けることで関係を良好にすることも可能です。
このような記事がそのきっかけになれば幸いです。
このブログでは、ADHD当事者の体験談の記事も書いています。