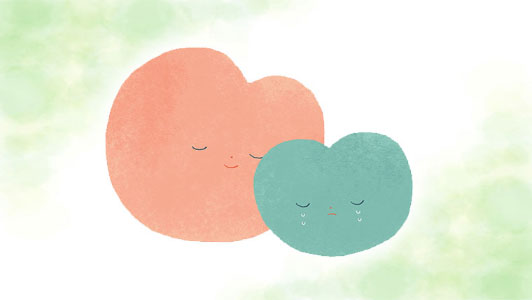ADHD・グレーゾーンでも大丈夫!新社会人が3ヶ月で職場に慣れるステップ解説
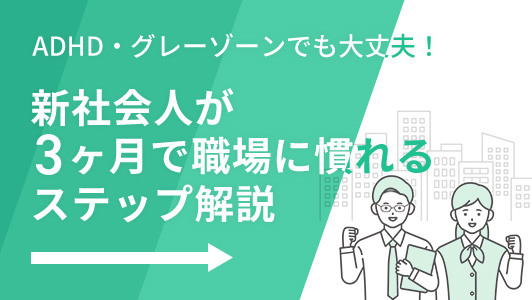
今年も新年度が始まりました。
「ADHDの自分でも、ちゃんと働けるのかな…?」
「普通の人より苦手なことが多いけど、仕事についていけるだろうか」
そんな不安や緊張を抱えて、働き始めた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ADHDやグレーゾーンの新社会人が、職場に少しずつ慣れていくための考え方や工夫を紹介します。
3ヶ月のステップに分けて、具体的な対応のコツをわかりやすく解説しています。
筆者自身も当時はADHDグレーゾーンで、悩みながら社会人生活をスタートしました
「自分にもできそう」と思えることが見つかれば嬉しいです。
ADHDと新社会人という大きなスタート
「なんとなくしんどい」その正体は?
新社会人になって、「なんだか毎日つらい」と感じていませんか?
疲れやすさや集中できない感じは、気持ちの問題だけではないかもしれません。
もしかすると、生まれつきの脳の特性が関係している可能性があります。
ADHDとグレーゾーンの人が感じやすい職場の壁
ADHDやグレーゾーンの人は、職場の環境に慣れるまで時間がかかる傾向があります。
たとえば、指示をうまく覚えられない、時間に追われてパニックになる。人間関係で「空気が読めない人」と見られてしまうこともあるでしょう。
人よりできないことが多いことから、疎外感や自責の念を感じてしまい、馴染みにくくなっているのです。
でも、自分に合った方法で対応していけば、少しずつ慣れていけます。
障害の有無に関係なく、新社会人はみんな大変
これは、発達障害に甘えてはいけないということではありません。
定型発達の人でも、中途入社のベテランでも、新しい職場には時間をかけて慣れていくものです。
焦らず、自分のペースで、できることを一つずつ積み重ねていきましょう。
仕事上でADHD特性とうまく付き合う考え方
具体的な方法を紹介する前に、知っておいて欲しい心構えがあります。ADHD持ちに限らず、新社会人には以下のような思考が大切です。
「できない自分を責めない」ための視点を持とう
失敗が続くと、「自分は社会人に向いていないのかも」と感じることがあるかもしれません。
でも、それは努力不足ではなく、「できない理由がある」ことがほとんどです。
自分を責めるより、「なぜできなかったのか」「どう対応できるか?」に目を向けていきましょう。
「努力不足」ではなく「脳のクセ」と知ることが第一歩
ADHDの特性は、集中力や記憶、感情のコントロールに影響します。
これは気合や根性では変えられない、脳の“クセ”のようなものです。
特性や仕組みを知ることで、自分に合った工夫や対策が見つけやすくなります。
すでに療育を受けてきた人は、自分用のやり方があるかもしれません。それを職場用にアレンジするのが、次のステップになります
メガネと同じ。工夫や補助ツールは「甘え」じゃない
メモやアプリ、タイマー、チェックリストを使うのは悪いことではありません。
自分の苦手を補う工夫は、甘えではなく「自分や周りを助ける手段」です。
もしかしたら、同僚はこういった工夫なしで仕事ができてしまうかもしれません。でも、比べて落ち込んだり、焦ったりしないでください。
あなたにはあなたのやり方があります。
視力が弱い人がメガネを使うように、補助ツールも前向きな選択肢の一つです。「自分を助けるために、何が使えるか」を考えてみてください。
ADHD新社会人が3ヶ月で職場に慣れるための3つのステップ
・職場の情報や環境を少しずつ整理しておこう
・毎日のリズムをなんとなくつかんでみよう
・上司や先輩との交流には、できる範囲で応えよう
・覚えた仕事や人付き合いを「形」や「パターン」として整理してみよう
・得意なことややりやすいスタイルを少しずつ伸ばしていこう
・3ヶ月はまだスタート地点。焦らず長い目で仕事を覚えていこう
【1ヶ月目】仕事は最低限でOK。まずは安心できる環境を作ろう
安心できる環境をつくる
最初の1ヶ月は、わからないことばかりで不安になって当然です。
まずは「安心して出勤できる環境」をつくることを意識してみてください。
ADHDの人は「曖昧なこと」が苦手なので、以下のようなポイントを明確にしておくと安心です。
- 自分の直属の先輩は誰か
- 困った時の質問、相談先はどこか
- 絶対にしてはいけないこと、ミスは何か
特にわからないことが多いこの時期は、すぐに質問・相談できる人を確保することが大切です
もし、職場の雰囲気が合わずに不安な場合は、「自分の中に安心の軸」をつくるのが効果的です。
たとえば、次のような行動を「毎日のルール」にしてみてください。
- 朝起きたらコーヒーを飲む
- 出勤前はカバンの中をチェックする
- 職場についたら挨拶をする
- 仕事の前に軽くストレッチする
- 「今ここまでやっています」と1日1回は報告する
- 帰宅後は服をハンガーにかける
環境に振り回されても、自分で決めた行動がひとつでもあると気持ちが安定しやすくなります。
仕事は最低限でOK
新人が任される仕事は、基本的に簡単で負担も責任も少ないものが多いです。
緊張しすぎず、「まずは試してみよう」という気持ちで取り組んで大丈夫。
ADHDの人はミスを恐れて完璧を目指しがちですが、最初から100点は必要ありません。少し肩の力を抜いていきましょう。
筆者は100点を目指して40点になる新人でした。
当時先輩がかけてくれた、「新人の失敗をフォローするのも先輩の仕事だから、気負いすぎないでね」という言葉が、今でも印象に残っています
生活リズムを「ざっくり」つかむ
仕事に慣れないうちは、寝坊や疲労でのダウンを防ぐために、平日の生活リズムをゆるく決めておくと安心です。
- 起きる時間
- 出勤準備にかかる時間
- 通勤にかかる時間
- 毎日する仕事(朝礼・会議など)
- 退勤時間
細かく完璧に決めなくても、だいたいの流れが見えているだけで動きやすくなりますよ。
上司や先輩の声がけに、できる範囲で応えよう
この時期は、上司や先輩が新人の様子を気にかけてくれることが多いです。
すべてに応える必要はありませんが、あいさつや短い返答でも好印象につながります。
ちょっとした会話から関係づくりがうまくいくことも多いです。人付き合いが苦手な人も、少しだけ勇気を出してみてください。
また、「自分の歓迎会」「部署の懇親会」「同期の集まり」の3つには、一度だけでも顔を出してみると、後々の人間関係が楽になるのでおすすめです。
ゲームでいうと“後につながる伏線イベント”のようなもの。無理のない範囲で参加を検討してみてください
【2ヶ月目】仕事の方法や人付き合いに「型」をつけてみよう
少し職場に慣れてきたら、日々の行動に「ルール」や「パターン」をつけてみましょう。
たとえば、
- 質問するときの言い方を決めておく(例:「確認なのですが〜」)
- 相談のタイミングを午前と午後で1回ずつと決めておく
- 自分だけの“仕事マニュアル”をつくってみる
- 集中タイムと会話タイムを意識して分ける
- 飲み会やイベント参加の判断基準を決めておく
などです。
ADHDの人は臨機応変な対応が苦手な傾向があります。
だからこそ、あらかじめ「こうする」と決めておくことで、心の負担が軽くなります。
2ヶ月目になると、仕事の流れや職場の雰囲気も見えてくるはず。今の自分に合った“型”を、少しずつ試してみましょう。
【3ヶ月目】「自分なりの成果の出し方」を見つけよう
3ヶ月目になると、得意なことややりやすい仕事の進め方が見えてくる人も多いです。
たとえば、「短時間なら集中できる」「誰かと話すとアイデアが出やすい」など。
自分では気づきにくい場合は、同期や先輩に「自分ってどう見えますか?」と聞いてみるのもアリです。
意外な強みに気づくきっかけになるかもしれません
見えてきた得意分野に工夫を加えることで、成果や自信にもつながります。
ADHDやグレーゾーンの人は、「周りと同じ」ではなく、「自分ができる貢献のしかた」を探していくことが、長く安定して働けるコツです。
おわりに:最初の3ヶ月を乗り切ったあなたへ
「3ヶ月たっても、まだ仕事ができない…」「ADHD特性が出てミスしてしまった」
そんな気持ちになっている人も、大丈夫です。
社会人としての道は、ここから何年、何十年と続いていきます。最初は失敗ばかりでも、それを乗り越えてきた経験こそが、あなたの力になります。
変化はゆっくりですが、3ヶ月、半年、1年後に振り返ると、きっと成長を実感できます。
今はまだスタート地点です。少しずつ、自分らしく働いていきましょう
このブログでは、他にもADHDの仕事について記事を書いています。